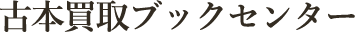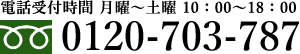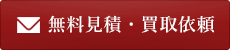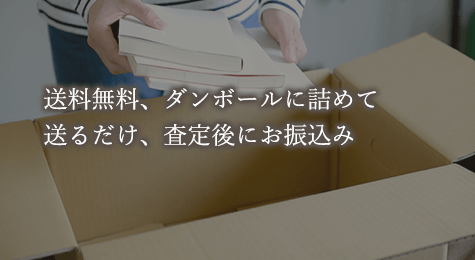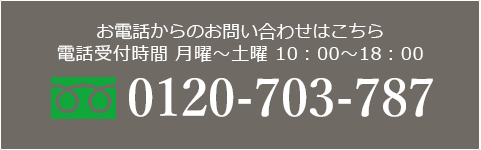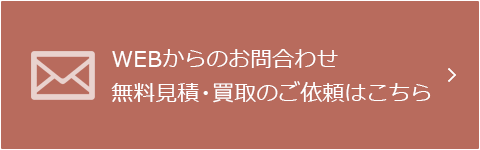小林斗庵・小篆千字文等書道書入荷しました。小林斗庵の本は以前1度紹介させていただいたことがあります。ご興味ある方はこちらもご覧ください。







小篆千字文を書いて
篆書の千字文を書きませんかという甘言に乗せられて、それでは小篆千字文の決定版を作ってやろうと、この二月から作業に入った。 千字文の作品は、智水の真草千字文以来、名家の作品も多いが、篆書のそれは意外に少ない。然も清朝に入ってから漸く書かれたようで、私 の知る限りでは、王虚舟、呉譲之、翁同蘇、王福園、わが国では西川春洞、内藤江月など、数える程しかなく、その上公刊されないものが多い。
初学が家書を学ぶには小篆から入るのが常識といってよいが、純正な小篆様で書かれた千字文は、呉譲之(未刊)と内藤江月の二種のみとい ってよい。ただ前者は緊密な構成に欠け、後者も結体や分間の問題に対する配慮が足りない。
小篆の構成は、縦画は垂直に、横画は水平に、左右相称に、点画は太細のないようにすべしと言われ、唐の李陽冰による玉筋象が理とされて、清朝の中期まで伝承され、針金を折り曲げたような無味乾燥なものになってしまった。 榮家を現代に復活したと称される鄧完白でさえ、五十歳の頃漸く堅苦しい玉筋篆から解放されて、晩年の剛毅奔放な境を開拓したのである。
左右相称的な規範を脱却して、自然な運筆、恣意的な結体を試み、秦篆の精華を現代に蘇生させた。鄧を尊敬した包世臣の『安呉論書』によっ て、その書は解析され、清朝第一の作家と称賛された。 包の弟子呉譲之によって都雅に洗練され、つづく趙之謙は前述の法則などを無視した、自在闊達の境を拓いた。 小象という書体を他の書体と伍して、観賞の対象とすることが出来たのは、右の三家以後といってよいのではないか。より古い金文などの書 体も、この開放的な風潮を承けて、さまざまな意匠を展開することが出来たといってよい。
さて、小家 予文を書く段になって、先ず考えた。第一に小篆の手本という命題を担うので、呉譲之もよし趙之謙もよしと、あまり自分の時灯に片寄ってはいけないことになる。結局、温雅で純正な呉譲之あたりを標準にすることで、草稿を作りはじめた。 -これより先、千字文は梁の時代に作られたので『説文解字』にない文字が大分ある。それをどうするか、先人の作品を彼此参照して字形を決 めていった。又、「〇文」の字形で明らかに間違っているものは、不徹底ながら少しく訂正しておいた(例=高・長・章・回)。
本来、水中に書くべき横画が、とかく右肩上りになる、左右相称はあまり気にしない、比較的書写の速度が早いので、末筆が縣心針象になる等 等、規格にそむく書きぶりが多いから、習う人は適当に勘案して欲しい。又、千字をつづけて一度に書くのは到底困難な業で、時を隔てて書き 継くという過程で、主人用筆結体等の一貫性を欠いたようだ。